 | 
シャトー・ラグランジュの歴史は中世にまで溯る。当時「ラグランジュ・モンテイユの高貴な館」と呼ばれており、領地の一部はボルドー聖堂騎士団に所属していた。1842年から1875年にかけて、シャトー・ラグランジュは、第一期の黄金時代を迎える。当時の所有者は、ルイ・フィリップ朝の元内務大臣デュシャテル伯爵で、この時代にグランクリュの第3級に選定されている。その後、経済的な困窮による「暗黒時代」が訪れたが、1983年12月、サントリーが購入し、佐治敬三社長と鳥井信一郎副社長(当時)の号令の下に巨額な投資を行うとともに、ワイン生産・経営陣にマルセル・デュカス、鈴田健二を任命、畑から醸造・貯蔵設備にいたる徹底的な再構築を断行した。その努力により、現在シャトーは、目をみはるような復興を成し遂げている。
シャトーの敷地は、AOCサンジュリアン内に地続きでひとつにまとまり、総面積は157ヘクタール。そのうち畑は114ヘクタール(赤100ヘクタール、白4ヘクタール)あり、ギュンツ土層由来の砂礫土壌からなるふたつの小丘に広がっている。栽培されている葡萄品種の割合は、カベルネ・ソーヴィニヨン種65%、メルロ種28%、プティ・ヴェルド種7%。 | |  | 
ル・クラスマンはシャトー・ラグランジュについて「特筆に値する厳格なセレクションによってシャトー・ラグランジュは堅牢で色が濃く、古典的なメドックのタンニンを持つ、実に安定したワインを産出している。」 として★★付高評価しています。 | |  | 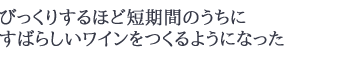
日本の大企業であるサントリーに買収されたのは1983年だが、同社はシャトーとシェ(ワイン蔵)だけでなく、畑にも並はずれた改良を加え始めた。出資はいっさい惜しまなかったため、管理を行うマルセル・デュカスや、このシャトーの若くて熱心なエノロジストである鈴田健二といった有能な人々が、びっくりするほど短期間のうちにすばらしいワインをつくるようになった。
ワインの品質が向上しただけでなく、ラグランジュはいまや、静かな庭や、白鳥やカモが集う湖がある美しいシャトーとなったのである。

1985年以降のヴィンテージに何か特別なスタイルが見られるとしたら、印象的な風味の深みと密着したたっぷりのタンニン、香ばしい新樽、下地となる多汁性とふくよかさだろう。厳しい選別と、シュルマテュリテ(ブドウが過熟すること)の要素を持つ非常に熟したブドウを収穫しているおかげであるのは間違いない。明らかにこの新しい当主は20年強も熟成できるのに若いうちから魅力のあるワインをつくろうとしているようだ。
世界のマスコミは、メンツェロプロス家によるシャトー・マルゴーの並はずれた方向転換を喝采してきたが、1990年には『ウォール・ストリート・ジャーナル』紙が手本とすべき成功例として取り上げていたことには驚かされたものの、シャトー・ラグランジュにおける変化についてはあまり書いてこなかった。それでも今なお、このワインの価格は、向上してきた品質レベルにしてはかなり低く抑えられている。

1960年代、1970年代には凡庸なワインをつくっていたが、日本のサントリーに買収されてからは目覚しくよくなった。現在の格付けに見合う価値があるが、サン=ジュリアンの他の有名シャトーと比べるとまだ知名度が低いため、それなりの良好なお値打ち品となっている。
ロバート・パーカー | | |  | レ・ザルム・ド・ラグランジュ 2011年 シャトー・ラグランジュ
ラグランジュの面積113haのうちこの白ワインの面積はわずか4haのみという非常に少量生産の白ワインでもあります。ソーヴィニヨン・ブラン種60%、セミヨン30%、ミュスカデル10% 「少量の良質な白ワイン」というコメントでクラスマンも注目。
品種特有のハーブの香りが個性的。凝縮された果実味、しっかりした酸味に恵まれ、数年後さらに大きく開花する白ワインです。ハーブを使ったグリルや白身系の肉料理にぴったりです。
透明ビンに入った麦わら色のきれいなカラーのレ・ザルムは、思わず手に取って飲んでみたくなるような欲望にかられるようなワインです。 | | |